「株のトークン化とは、最近よく聞くけれど一体何だろう」「トークン化とは何ですか?と聞かれても、うまく説明できない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
株式投資や暗号資産に関心がある方なら、この新しい技術がもたらす可能性とリスクについて、正確に理解しておきたいところです。
金融の世界が大きく変わろうとしている今、この革新的な仕組みを知ることは、未来の資産形成を考える上で非常に大切になります。
この記事では、株のトークン化とは何かという基本的な知識から、その仕組み、メリットやデメリットに至るまで、専門的な内容を分かりやすく解説していきます。
この記事を読むことで、以下の4つの点が明確になります。
ポイント
- トークン化株式の基本的な仕組み
- 従来の株式投資との具体的な違い
- 投資家が知るべきメリットと注意点
- 日本における現状と将来性
この記事の目次
株のトークン化とは?基本をわかりやすく解説
メモ
- そもそもトークン化とは何ですか?
- 株式がデジタル資産になる仕組み
- 現物株やCFDとの違いを比較
- 24時間365日いつでも取引可能
- 小口化でフラクショナル投資を実現
- DeFiと融合するプログラマビリティ
そもそもトークン化とは何ですか?

トークン化とは、株式や不動産、美術品といった現実世界のさまざまな資産の価値を、ブロックチェーン技術を使ってデジタルの「トークン」に変換するプロセスを指します。
このトークンは、資産の所有権や権利を表すデジタル証明書のようなものと考えると分かりやすいかもしれません。
例えば、あなたが価値のある絵画を持っているとします。
この絵画を安全な金庫に預け、その所有権を証明する暗号化されたデジタル証明書を発行します。
この証明書はインターネット上で瞬時に、そして安全に売買できるようになり、その価値は金庫の中にある絵画の価値と完全に連動します。
これがトークン化の基本的な考え方です。
ブロックチェーンは、取引記録を鎖のようにつなげて管理する技術で、改ざんが非常に難しいという特徴を持っています。
そのため、トークン化された資産の所有権の移転履歴は、透明性高く、かつ安全に記録され続けます。
このように、トークン化は既存の資産にデジタルの利便性と安全性を与える画期的な手法と言えます。
株式がデジタル資産になる仕組み

株式のトークン化は、前述したトークン化の仕組みを、上場企業の株式に応用したものです。
その中核には「1対1の資産裏付け」という厳格な原則が存在します。
これは、市場に流通するトークン1枚ごとに、実物の株式1株が金融機関によって確実に保管されていなければならない、というルールです。
この仕組みを実現する方法には、主に2つのモデルがあります。
発行者とプラットフォームが分離したモデル
これは最も一般的なモデルで、株式をトークン化する「発行者」と、そのトークンを投資家が売買する「取引プラットフォーム」の役割が分かれています。
まず、規制された専門の発行者が、証券会社を通じて本物の米国株などを購入します。
購入された株式は、発行者や取引プラットフォームとは別の、信頼性の高い第三者カストディアン(保管業者)に預けられます。
この資産保全が確認された後、発行者はブロックチェーン上で同数のトークンを発行し、それが暗号資産取引所などのプラットフォームで流通する流れです。
垂直統合型モデル
こちらは、米国のRobinhoodなどが採用するモデルで、プラットフォーム自身が証券ライセンスを持ち、発行者としての役割も兼ねます。
自社で株式を取得・保管し、それに対応するトークンを自社のプラットフォーム内だけで発行・取引させます。
外部の事業者が介在しないため、エコシステムとしては閉鎖的ですが、一貫したサービスを提供できるのが特徴です。
いずれのモデルも、トークンの価値が実際の株価に連動し、配当が出た場合はトークン保有者が同等の経済的利益を受け取れるように設計されています。
現物株やCFDとの違いを比較

トークン化株式は、これまでの金融商品と何が違うのでしょうか。
ここでは、従来からある「現物株式」や「CFD(差金決済取引)」と比較してみましょう。
それぞれの特徴を理解することで、トークン化株式の位置づけがより明確になります。
上の表から分かるように、トークン化株式は現物株式の「資産の裏付け」という信頼性と、CFDや暗号資産の「取引の柔軟性」を兼ね備えていると考えられます。
特に、24時間取引可能で決済が速い点、そしてDeFi(分散型金融)との連携が可能である点は、他の金融商品にはない大きな特徴です。
ただし、法的な所有権は直接持たないため、議決権の行使などが制限される場合がある点には注意が必要です。
24時間365日いつでも取引可能

トークン化株式がもたらす最も大きな変革の一つは、取引時間の制約からの解放です。
ニューヨーク証券取引所や東京証券取引所など、従来の株式市場には「取引時間」という明確な区切りがあります。
市場が閉まっている夜間や休日に、たとえ企業に関する重大なニュースが発表されても、投資家は市場が再開するまで待つしかありませんでした。
一方、トークン化株式はブロックチェーン上で取引されるため、市場が閉まるという概念がありません。
理論上、24時間365日、いつでも取引が可能になります。
これにより、アジアの投資家が欧米の市場が開くのを待つ必要も、その逆もなくなります。
世界中の投資家が、それぞれの生活スタイルに合わせて、いつでも市場に参加できるのです。
この特徴は、グローバルなニュースや経済指標の発表に対して、リアルタイムで対応できることを意味します。
例えば、米国企業の決算が取引時間外に発表された場合でも、即座に売買の判断を下せるようになります。
このように、眠らない市場が生まれることで、世界中の流動性が一つの市場に集約され、より効率的な価格形成が期待できるのです。
小口化でフラクショナル投資を実現

従来の株式投資では、特に優良企業の株は1株あたりの価格が非常に高額で、個人投資家が手を出しにくいという課題がありました。
例えば、世界的に有名な投資家ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイのクラスA株式は、1株数千万円にもなり、購入できる人はごく一部に限られます。
トークン化株式は、この課題を解決する「フラクショナル所有(分割所有)」を容易に実現します。
1株の価値を、デジタルの力で0.1株や0.01株といった非常に小さな単位に分割して取引できるようにするのです。
これにより、これまで資金的な制約で投資できなかった高額な株式にも、数千円や数万円といった少額から投資できるようになります。
これは、投資の機会をより多くの人々に開く「投資の民主化」とも言える動きです。
複数の有名企業の株式に少額ずつ分散投資してポートフォリオを組む、といった戦略も立てやすくなります。
このように、トークン化は資産形成のハードルを大きく下げ、誰もが世界経済の成長に参加できる可能性を秘めています。
DeFiと融合するプログラマビリティ

トークン化株式の隠れた、しかし非常に強力な特徴が「プログラマビリティ(プログラム可能性)」です。
これは、トークンがブロックチェーン上の「スマートコントラクト」というプログラムで管理されていることに由来します。
従来の証券口座に保管されている株式は、基本的には値上がりを待つか配当を受け取るだけの、いわば「眠れる資産」でした。
しかし、トークン化された株式は、DeFi(分散型金融)と呼ばれる新しい金融エコシステムの中で、さまざまな形で活用できる「動的な資産」に変わります。
例えば、保有しているトークン化株式を担保にして、暗号資産(ステーブルコインなど)を借り入れることができます。
また、トークン化株式をDEX(分散型取引所)の流動性プールに提供することで、手数料収入を得る(イールドファーミング)といった、新たな収益機会も生まれる可能性があります。
このように、他の金融サービスと自由に「組み合わせる」ことができる性質は「コンポーザビリティ」とも呼ばれ、これまでの金融の世界では考えられなかったような、革新的な資産運用戦略を可能にします。
トークン化株式は、単なる株式のデジタル版にとどまらず、次世代の金融インフラの構成要素となるポテンシャルを秘めているのです。
リスクと未来、株のトークン化とはどうなる?
メモ
- 規制の不透明性と法的な課題
- 発行者の信頼性が問われるリスク
- スマートコントラクトの脆弱性
- 日本で株式トークンは発行できるか
- ほふりとの二重管理問題とは
- まとめ:結局、株のトークン化とは何か
規制の不透明性と法的な課題

トークン化株式は革新的な技術ですが、その普及における最大の逆風となっているのが、法規制の不透明性です。
これは新しい金融商品であるため、世界各国の法整備がまだ追いついていないのが現状です。
国や地域によって、トークン化株式がどのような法的位置づけになるのか、どのようなライセンスが必要なのかが異なり、投資家保護の枠組みもさまざまです。
特に、米国の証券取引委員会(SEC)は、個人投資家向けの商品としてトークン化株式を現時点では広く認可していません。
このため、多くのプラットフォームは、米国以外の投資家を主なターゲットとしてサービスを展開しています。
また、法的な権利の側面も課題です。
トークン化株式の保有者は、裏付けとなる株式の経済的な利益(株価変動や配当)は受けられますが、法的な株主として認められるわけではありません。
つまり、株主総会での議決権や株主優待といった、本来の株主が持つ権利が付与されないケースがほとんどです。
この点は、現物株式への投資とは根本的に異なるため、投資家は自身が何を所有しているのかを正確に理解しておく必要があります。
発行者の信頼性が問われるリスク

トークン化株式の価値は、そのトークンが実物の株式によって1対1で確実に裏付けられているという「信頼」に基づいています。
この信頼を揺るがしかねないのが、発行者やカストディアン(保管業者)が破綻したり、不正を働いたりする「カウンターパーティリスク」です。
たとえトークンがブロックチェーン上で安全に管理されていても、その裏付けとなる実物の株式を保管している金融機関が倒産してしまえば、トークンの価値は無くなってしまう可能性があります。
過去に、大手暗号資産取引所であったFTXが破綻した事件は、プラットフォーム運営者の経営や倫理がいかに大切かを痛感させました。
FTXが提供していたトークン化株式サービスも、経営破綻によって終了しています。
この事件は、トークン化の仕組み自体に問題があったわけではなく、運営者の不正が原因でした。
この教訓から、投資家はトークン化株式を選ぶ際に、どの企業が発行し、どこに資産が保管されているのかを慎重に確認することが求められます。
規制当局から正式なライセンスを受けているか、信頼性の高い第三者機関による監査を受けているか、といった点がプラットフォームを選ぶ上での重要な判断基準となります。
スマートコントラクトの脆弱性

トークン化株式は、ブロックチェーン上の「スマートコントラクト」というプログラムによって、発行や移転が自動的に実行されます。
ブロックチェーン技術自体は改ざんが困難で非常に堅牢ですが、その上で動くスマートコントラクトのコードにバグや設計上の欠陥(脆弱性)が存在する可能性はゼロではありません。
もしスマートコントラクトに脆弱性があれば、悪意のあるハッカーによって悪用され、トークンが不正に送金されたり、システムが停止したりするリスクが伴います。
DeFiの世界では、実際にスマートコントラクトの脆弱性を突かれて巨額の資産が流出する事件が過去に何度も起きています。
もちろん、信頼できる発行者が提供するトークン化株式は、専門家による厳格なコード監査を複数回受けるなど、セキュリティ対策に万全を期しています。
しかし、どのようなソフトウェアにも100%の安全は保証されないという事実は、技術的なリスクとして認識しておくべきです。
投資家としては、プラットフォームがどのようなセキュリティ対策を講じているか、過去の実績はどうかといった点にも注意を払うことが望ましいでしょう。
日本で株式トークンは発行できるか

日本においても、不動産などを裏付けとしたセキュリティトークン(ST)市場は徐々に成長していますが、米国企業の上場株式などを対象としたオープンなトークン化株式は、まだ本格的に流通していません。
これには、日本の法制度や金融インフラに起因する、いくつかの「壁」が存在します。
金融商品取引法とPTS規制
まず、法制度の壁です。
不特定多数の投資家が自由に売買できるようなトークン化株式を発行することは、日本の金融商品取引法上、「公募」と見なされる可能性が高いです。
その場合、発行体には有価証券届出書の提出など、非常に厳しい情報開示義務が課せられます。
また、現在日本でSTが流通できるのは、ODX(大阪デジタルエクスチェンジ)の「START」のような、認可されたPTS(私設取引システム)に限られています。
PTSは参加できる証券会社などが限定された「閉じた市場」であり、世界中の誰もが匿名で参加できるDeFiのようなオープンな環境とは根本的に思想が異なります。
このように、投資家保護を最優先する日本の規制体系が、オープンなトークン化株式の展開を難しくしている一因です。
【独自】SBIが新会社設立へ ブロックチェーンで株式を“デジタル化” 新興企業Startaleと合弁
シンガポールのWeb3新興スターテイルと共同でブロックチェーンを使った金融取引基盤の開発へ
株式をトークン化し、証券取引所を仲介せず、最短で数秒の取引時間、手数料も殆ど不要にhttps://t.co/OrIAZVk9hV pic.twitter.com/TCGXvsjZ4J— 漣改🇯🇵 (@sazanamimod) August 21, 2025
ほふりとの二重管理問題とは
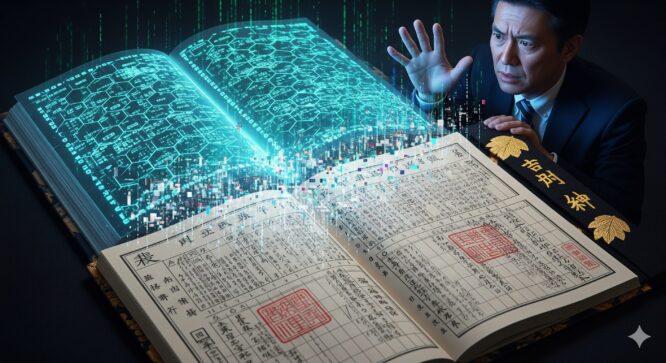
日本でオープンな株式トークン化を実現する上で、最大の障壁とも言えるのが金融インフラの問題、特に「ほふり」(証券保管振替機構)との関係です。
ほふりは、日本の上場株式の所有者情報を電子的に一元管理している、いわば「公式な正本台帳」です。
誰がどの会社の株を何株持っているかという記録は、すべてほふりのシステムによって法的に担保されています。
ここに、ブロックチェーンというもう一つの台帳を持ち込むと、「二重管理」という深刻な問題が生じます。
もし、ブロックチェーン上の記録とほふりの記録に食い違いが生じた場合、法的にどちらが真の株主として扱われるのでしょうか。
財産権の帰属に大きな混乱を招く可能性があります。
さらに、配当の支払い、議決権の行使、株式分割といった複雑な手続き(コーポレートアクション)を、ほふりのシステムとブロックチェーン上の無数のトークン保有者の間で、遅延なく正確に同期させることは技術的にも非常に難易度が高い課題です。
この強力な中央集権インフラの存在が、米国型のオープンな株式トークン化を日本でそのまま導入することを困難にしている最大の要因と考えられます。
まとめ:結局、株のトークン化とは何か
最後に、この記事で解説した「株のトークン化とは何か」について、重要なポイントをまとめます。
- トークン化とは現実資産の価値をブロックチェーン上のデジタルトークンに変換する技術
- 株式のトークン化は企業の株式をデジタル化したもの
- トークンの価値は実物の株式と1対1で裏付けられるのが原則
- ブロックチェーン上で管理されるため透明性と安全性が高い
- 法的な株主ではなく裏付け資産の経済的利益を得る権利を持つ
- 最大のメリットは24時間365日取引が可能になること
- 高額な株式も少額から投資できるフラクショナル所有が容易になる
- 決済スピードがほぼ即時で資金効率が向上する
- 地理的な制約が少なくグローバルな市場アクセスが可能になる
- DeFiと連携させることで新たな資産運用が期待できる
- 一方で法規制が未整備で国によって扱いが異なる点がリスク
- 発行者や保管業者の信頼性が資産価値を左右する
- スマートコントラクトの技術的な脆弱性も注意点の一つ
- 日本では「ほふり」との二重管理問題が大きな障壁となっている
- 金融市場のインフラを根本から変える可能性を秘めたイノベーションである
