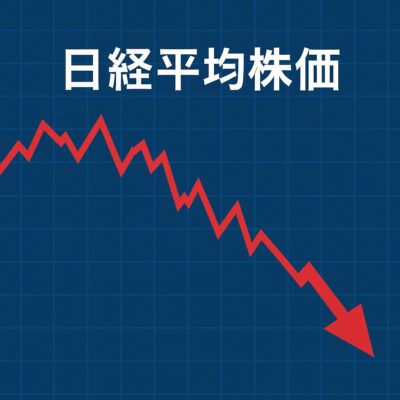「日経平均株価が下がるとどうなるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
株式投資をしていない人でも、経済ニュースで日経平均の急落を目にすれば不安を感じるものです。
本記事では、日経平均株価が下がるとどうなるのかをわかりやすく解説し、生活や企業活動への影響にもお答えします。
また、「株価が下がるのに儲かる人がいるの?」「逆に上がる株もあるの?」といった視点や、「日経平均株価は何に影響されますか?」といった基本的な理解まで網羅しており、これから経済や投資について学びたい方にも最適な内容です。
ポイント
・日経平均株価が下がると生活や企業にどんな影響が出るか
・株価下落時に儲かる人やその仕組み
・日経平均が下がっても上がる株がある理由
・日経平均株価が何に影響されて動くのか
この記事の目次
日経平均株価が下がるとどうなるのか解説
メモ
・わかりやすく解説
・株価が下がるとどうなるんですか?
・企業側のデメリット
・生活はどうなる?
わかりやすく解説
日経平均株価が下がるという現象は、日本の経済や企業の状況が悪化しているという「シグナル」として広く捉えられています。
株式投資をしていない人にとっても、決して無関係ではありません。

まず、日経平均株価とは、東京証券取引所に上場している代表的な225社の株価をもとに算出される指数です。
これが下がるということは、多くの企業の株価が同時に値下がりしている状態を意味します。
企業の業績悪化や将来への不安が投資家の売りを招き、その結果として平均株価が低下していくのです。
日経平均株価の下落が続くと、企業の時価総額が減少し、資金調達が難しくなります。
その影響で新しい設備投資が見送られたり、人件費削減のために採用を控えたりするようになります。

また、消費者の心理にも影響が出ます。
株価が下がることで将来への不安が強まり、財布のひもが固くなる傾向が見られるのです。
これを経済学では「逆資産効果」と呼びます。
家計が実際に減っていなくても、株価が下がっているという情報だけで支出を控えるようになり、消費が冷え込むことがあります。
さらに、株式を保有している人にとっては資産の目減りを意味します。
年金や保険商品が株式投資を含んでいる場合もあり、それらの運用成績にも悪影響を及ぼすでしょう。
このように、日経平均株価の下落は投資家だけでなく、一般家庭や企業、さらには国全体の経済活動にも波及していく可能性があるのです。
株価が下がるとどうなるんですか?
株価が下がると、まず最も直接的な影響を受けるのは「その株を保有している人たち」です。
株価が下がれば、持っている株式の価値が減ってしまいます。

もし株価が下がった時点で売却すれば、損失は確定されてしまいます。
しかし、影響はそれだけにとどまりません。
企業側にとっても、株価の下落は大きな問題になります。
というのも、株価は企業の将来に対する評価でもあるからです。
企業が資金を調達しようとして新たに株式を発行したとしても、株価が安ければ集められる資金も少なくなってしまいます。
たとえば、100万株を1,000円で発行すれば10億円を集められますが、800円でしか売れなければ8億円にしかなりません。
この差は非常に大きく、事業の拡大計画にも影響を与えます。

「あの会社、大丈夫なの?」という不安が取引先や銀行、就職を考えている人々に広がることもあります。
これにより、優秀な人材が集まりにくくなったり、銀行が貸し渋ったりするケースもあるのです。

株価が下がって企業の価値が市場で低く評価されると、外部から「買い叩かれる」可能性が出てきます。
特にグローバルな視点では、日本企業が海外企業に買収されるリスクも無視できません。
株式市場全体の株価が下がると、経済全体にも悪影響が広がることがあります。
株価は景気の先行指標とされており、多くの投資家が景気の悪化を見越して売りを加速させることで、さらなる下落を招くこともあるからです。
このような連鎖反応が起きると、株価の動きは個人の問題にとどまらず、社会全体の不安材料へと変化していきます。
株価の下落は、個人・企業・社会それぞれに広く影響を与える問題であると理解しておくことが大切です。
企業側のデメリット
企業にとって株価の下落は、数多くのデメリットをもたらします。
その中には直接的な損失だけでなく、間接的な信頼の失墜や経営判断の制限など、目に見えにくい問題も多く含まれています。
買収リスク
まず考えられるのは「買収リスクの高まり」です。
企業の株価が大幅に下がると、企業全体の時価総額も連動して小さくなります。
すると、その企業に魅力を感じている外部の大手企業やファンドなどが、買収を狙って株を買い集める可能性が出てきます。
株価が安いタイミングは「お買い得」と判断されやすく、敵対的買収の標的にされることもあります。
このような事態が起きれば、経営陣の入れ替えや事業の再構成、従業員のリストラなど、企業の現場に大きな変化をもたらすことになります。
ネガティブな空気
また、株価の下落は社内にもネガティブな空気を広げます。
自社株を保有している役員や社員にとって、自分たちの働きが市場で評価されていないと感じることはモチベーションの低下につながります。
とくにストックオプション制度を導入している企業では、株価が下がることで報酬インセンティブが機能しなくなる恐れもあるのです。
取引先への影響
さらに、長期的に株価が低迷すれば、取引先やパートナー企業にも影響が及びます。
株価の動きを敏感にチェックしている企業は、取引先の不安定な状態を見て契約の見直しや発注量の削減などを検討するかもしれません。
これにより、本来は順調に進んでいた取引が縮小されるケースもあります。
その他
そのほか、IR活動(投資家向け広報)やメディア対応にも時間とコストがかかる点も見逃せません。
株価が下がると、投資家からの問い合わせや説明責任が増え、経営者が本来取り組むべき事業の推進から時間を奪われるという側面もあるのです。
こうした多方面にわたるデメリットを回避するには、企業が自社の価値や将来性を正しく伝える努力を続けることが求められます。
透明性の高い経営と信頼に足る業績が、長期的な株価の安定につながるのです。
生活はどうなる?
日経平均株価が下がると、多くの人は「株を持っていないから関係ない」と思いがちです。
しかし、株価の動きは私たちの生活にもじわじわと影響を与えてきます。
直接的な影響ではなくても、間接的な形で暮らしに響いてくることは少なくありません。
企業側の反応
まず、日経平均株価の下落は、企業の業績や経済全体への不安感の現れとされるため、景気後退の兆しと受け取られやすくなります。
すると企業は守りの姿勢に転じ、設備投資や人材採用を控えるようになります。
その結果として、新卒採用の数が減ったり、派遣・アルバイトの契約更新が見送られたりすることがあります。
こういった影響は、直接雇用されている労働者だけでなく、その家族や地域経済にも波及します。
消費者側の反応
さらに、株価の下落は消費者心理にも大きな影響を与えます。
たとえば、「将来が不安だから、今はお金を使わずに貯めておこう」と考える人が増えることで、消費が抑制されます。
これにより、飲食・旅行・アパレルなどの消費関連産業では売上が落ち込み、収益悪化によってリストラや店舗閉鎖が進むこともあり得ます。
日本の物価が過去最高を更新しました(コアCPI)
3月インフレ率は3.6%となり、2%以上の状態が3年(36ヶ月連続)に達しました。
アメリカは2.4%で、G7で日本が一番インフレ率の高い国になっていますコメ5キロ5000円突破が目前。
物価高に苦しむ国民が増えています。
食料品の消費税ゼロ%が必要です pic.twitter.com/UFURVx7NWj— アンゴロウ@暗号資産 (@angorou7) April 18, 2025
このように、株価が下がることは巡り巡って消費と雇用の両方にブレーキをかける結果になりかねません。
年金や保険商品
また、私たちの将来に関わる「年金」や「保険商品」も無関係ではありません。
公的年金や多くの保険会社の運用は、国内外の株式市場に一定の比率で投資されているため、株価が大幅に下落すると運用成績が悪化する可能性があります。
これが長期的に続けば、将来の年金支給額や保険の利回りにも悪影響を及ぼす恐れが出てきます。
ローンへの影響
住宅ローンや自動車ローンを組んでいる人にとっても注意が必要です。
景気の悪化が現実味を帯びてくると、金融機関の審査が厳しくなり、新規の借入が難しくなるケースがあります。
また、勤務先の業績が悪化すれば、ボーナスカットや給与減額といった形で家計にも直撃します。
これが家計の見直しや支出削減を強いられる一因となり、生活の質にも影響を与えることがあるのです。
このように考えると、日経平均株価の下落は、証券口座を持っているかどうかに関係なく、少しずつでも生活に変化を与える可能性があります。
私たちの暮らしがどう動いていくのかを予測するうえで、株価の動きにも少し目を向けておくことは無駄ではありません。
日経平均株価が下がるとどうなるか投資視点で考察
メモ
・儲かるのは誰か
・上がる株の存在
・日経平均株価は何に影響されますか?
儲かるのは誰か
日経平均株価が下がると、「誰が儲かるのだろう?」という疑問が浮かぶかもしれません。
株価が下がることは一般的には経済にとって悪いニュースだと思われがちですが、実は下落を利用して儲けることができる人々も存在します。
空売りを行う人
一部の投資家、特に「空売り」を行う人たちがその代表的な例です。
空売りとは、保有していない株を借りて売り、株価が下がったところで安く買い戻すという手法です。
株価が下がると予測した投資家は、事前に株を売却し、後日その株を安い価格で買い戻すことで利益を得ます。
もし日経平均株価が大きく下がると、その利益は相当なものになります。
空売りを上手く活用する投資家は、株価の下落から利益を得ることができます。
ショートポジション
また、投資信託やヘッジファンドのようなプロの投資家たちも、株価の下落を見越して利益を得ることがあります。
これらの投資家たちはリスクを分散しつつ、市場の動向を精密に予測し、下落局面で利益を得られるようなポジションを取ることができます。
特に「ショートポジション」と呼ばれる、株価が下がることを予想して売りを行う戦略を取ることで、株価下落時に利益を得ることが可能です。
為替差益を得る
さらに、外国為替市場の投資家も日経平均株価の下落によって利益を得ることがあります。
株価が下がることで、円が一時的に弱くなることがあります。
この動きを予測して、円安を見越して外貨を買うことで、為替差益を得ることができます。
特に外国の投資家は、このような動きに敏感に反応し、株価の下落に合わせて利益を得ることが可能です。
インフレヘッジ
加えて、インフレヘッジや金に投資している人々も利益を得る場合があります。
株価が下落して市場全体が不安定になると、金の価格が上昇することがよくあります。
米国経済の失速が半端ない
世界経済も巻き込んで大幅株安に
有事の時は、やはり金(ゴールド)投資
最高値更新で3300ドル突破安全資産にシフト
金(ゴールド)に新NISAでも投資できる方法は
続↓ pic.twitter.com/etvJiAwkLu— あきにい@資産形成+お金のスペシャリスト (@kigurumi_m) April 16, 2025
これは、金が「安全資産」としての役割を果たすためです。
金に投資している投資家は、株価下落による影響を受けることなく、金の価値上昇によって儲けることができます。
このように、日経平均株価が下がると、株を持っていない人や普段株式市場に関わっていない人が必ずしも損をするわけではありません。
投資の世界には、下落相場を逆手に取って利益を上げる戦略を持った投資家もいるため、株価下落が必ずしも悪いニュースであるとは限らないのです。
上がる株の存在
日経平均株価が下がっているときでも、すべての株が一斉に下落するわけではありません。
むしろ、そのような下落相場で逆に株価を上げる「逆行高(ぎゃっこうだか)」の銘柄も存在します。
このような株の存在を知っておくことで、投資家は下落局面でもチャンスを見つけることができます。
ディフェンシブ銘柄
まず注目されるのが「ディフェンシブ銘柄」と呼ばれる業種です。
具体的には医薬品、食品、電力、ガスなど、景気に左右されにくい業種の企業です。
ジェネレーティブ AIにポートフォリオ見てもらったら、医薬品か食品入れろと。
・ディフェンシブ銘柄の追加
医薬品(例:武田薬品、アステラス)、食品(例:キッコーマン、味の素)、電力・ガス(例:東京電力、中部電力)などを1~2銘柄加えると、景気後退局面のリスクヘッジになります。— 怪盗キットカット (@KaitoKitkat) April 18, 2025
たとえば、景気が悪化しても人々は病院に行きますし、食料や電気・ガスの使用をやめることはありません。
このため、これらの業種に属する企業の業績は相対的に安定しており、日経平均が下がっても株価が上昇、または下落幅が小さくなる傾向があります。
インバース型ETF
次に「インバース型ETF」と呼ばれる金融商品もあります。
これは日経平均株価などの指数が下がると、反対に価格が上がる仕組みの投資信託です。
先行きがあまりにもわからないので、インバース型ETFでリスクヘッジすることにしました。
V字回復シナリオではなく、L字シナリオを踏まえて動いています。4割個別株式
2割インバース型ETF
4割手元資金
というディフェンス重視のフォーメーションで明日は臨む❗— 株ねこ (@o26tKOzDas79314) April 7, 2025
代表的な銘柄としては「日経平均ダブルインバース(1357)」などがあり、日経平均が2%下落すれば、約4%上昇するように設計されています。
投資経験がある程度ある人であれば、短期的なヘッジ手段として活用されることもあります。
金や債券
また、市場が混乱しているときには、安全資産とされる「金関連株」や「債券関連銘柄」が買われやすくなります。
これは、投資家がリスク資産から資金を引き上げ、安全性の高い投資対象に移動させる動きによるものです。
たとえば、金鉱関連企業や、長期債に連動するETFなどがその対象です。
中小型株
さらに、日経平均に大きく含まれていない中小型株が、独自の材料や成長ストーリーを持って上昇するケースもあります。
こうした企業は、日経平均の影響をあまり受けないため、地合いに関係なく上昇する余地があります。
このように、日経平均が下がる局面でも上がる可能性のある株や商品は少なからず存在します。
市場全体に目を奪われがちですが、個別に着目すれば多様な動きがあり、そこに投資のヒントが隠れていることもあります。
日経平均株価は何に影響されますか?
日経平均株価は、日本経済の象徴的な指標として広く使われていますが、その動きは単純な要因では説明しきれません。

ここでは、その主な影響要因をわかりやすく紹介します。
企業業績
まず大きな影響を与えるのが「企業業績」です。
日経平均は、東京証券取引所に上場する225社の株価から構成されており、これらの企業の業績が好調であれば、株価が上昇しやすくなります。
たとえば、トヨタ自動車やソニーといった大手企業が良い決算を出すと、日経平均も上昇傾向になる可能性が高くなります。
為替相場
また、「為替相場」も日経平均に強く影響します。
特にドル円の動きは注目されており、円高になると輸出企業の利益が圧迫され、株価が下がりやすくなります。
みんな株安に気を取られてるけど
円高進行もなかなかエグい pic.twitter.com/KUIhUCnK05— とんかつ@インデックス投資 (@tonkatsu_index) April 17, 2025
反対に円安が進むと、海外での売上が増える企業が恩恵を受け、日経平均は上昇しやすくなります。
輸出産業が日本の経済に占める割合が高いため、この傾向は長年変わっていません。
海外市場の動向
さらに、「アメリカを中心とした海外市場の動向」も見逃せません。
米国の主要な株価指数、たとえばダウ平均やNASDAQが大きく変動すると、それが翌営業日の日本市場に直接反映されるケースが多いです。
アメリカ経済の指標発表やFRB(米連邦準備制度)の金利政策なども、間接的に日経平均に波及します。
日本国内の金融政策
そのほか、「日本国内の金融政策」も影響を与える要因の一つです。
たとえば、日本銀行が金利を引き上げる可能性を示唆しただけでも、株式市場は反応します。
金利が上がれば企業の借入コストが増し、業績への懸念が広がるため、株価が下がりやすくなります。
投資家心理
最後に、「投資家心理」も無視できない要因です。
良くも悪くもニュースや政治的発言、地政学的リスクが投資家の心理に影響を与え、実体経済以上に株価が動くこともあります。
近年ではAIによるアルゴリズム取引の影響も強く、突発的な下落や上昇を引き起こす要因になっています。
このように、日経平均株価は多くの国内外要因に影響されており、単純な指標ではありません。
日々の値動きを理解するには、経済ニュースや企業の動向に関心を持つことが重要です。
日経平均株価が下がるとどうなるかを総まとめで解説
-
経済の悪化を示すシグナルとして受け取られる
-
企業の株価が下がり、時価総額も減少する
-
資金調達が難しくなり、設備投資が停滞する
-
雇用抑制や新卒採用の縮小が起こりやすくなる
-
消費者心理が冷え込み、支出が減少する
-
保有株の下落により資産が目減りする
-
年金や保険の運用成績に悪影響が及ぶ
-
景気後退への不安が社会全体に広がる
-
株価低迷により企業イメージが悪化する
-
銀行の融資姿勢が慎重になりやすくなる
-
海外からの敵対的買収リスクが高まる
-
社員の士気が下がり、組織内の活力が低下する
-
IR対応などで経営資源が分散される
-
株価下落局面でも上がる銘柄が存在する
-
空売りやインバース型ETFなどで利益を得る投資家もいる