海外の取引先への支払いや、留学中の家族への送金など、国際的なお金のやり取りが必要になった際に「SWIFT(スイフト)」という言葉を耳にしたことはありませんか。
このシステムは、単にお金を送るだけでなく、送金メッセージの仕組みそのものを指しています。
さらに、送金手続きには国際送金で使われるswiftコードが不可欠で、このコードは銀行ごとに定められています。
例えば、swiftコードの例:三井住友銀行などがそれに当たります。
一方で、スイフトコードとビックコードの違いは何ですか?といった類似用語に関する混乱や、最終的に気になるswift送金の手数料といったコスト面での不安を感じる方も少なくありません。
この記事では、これらの疑問を一つひとつ丁寧に解き明かし、SWIFTの全体像を明確にしていきます。
ポイント
- SWIFTがどのような組織で、何の略称なのかがわかる
- 海外送金におけるSWIFTの具体的な役割と仕組みがわかる
- SWIFTコードの構造や、銀行ごとのコード例がわかる
- 海外送金にかかる手数料の種類と注意点がわかる
この記事の目次
swiftとは何かをわかりやすく解説
メモ
- SWIFTとはどういうシステムですか?
- 「Swift」は何の略ですか?
- 海外送金でSWIFTとは何ですか?
- 送金メッセージの仕組み
- swift電文とはどんな情報のこと?
どういうシステムですか?

SWIFTとは、世界中の金融機関を結び、安全に金融取引に関するメッセージをやり取りするための巨大なネットワークシステムです。
重要なのは、SWIFT自体が資金を移動させたり、口座を管理したりする「銀行」ではないという点になります。その役割は、銀行間の送金指示などを正確かつ迅速に伝達する「メッセンジャー」に近いものです。
このシステムは、ベルギーに本部を置く非営利の協同組合によって運営されており、世界200以上の国や地域にある1万1,000以上の金融機関が加盟しています。
この広範なネットワークのおかげで、世界のほぼ全ての銀行間で、標準化された安全な方法で情報のやり取りが可能になっています。
このように、SWIFTは国際金融の根幹を支える社会的インフラとして機能しており、貿易決済や個人間の送金など、国境を越えるあらゆる金融取引に欠かせない存在です。
高いセキュリティと信頼性を備えているため、金融機関は安心してこのプラットフォームを利用できます。
何の略ですか?

「Swift」は、"Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" の頭文字を取った略称です。
これを日本語に翻訳すると、「国際銀行間金融通信協会」となります。
この名称が示す通り、SWIFTは個別の企業や国家に属する機関ではなく、加盟する世界中の金融機関が共同で所有する「協同組合」として設立されました。
1973年に設立される以前、国際的な金融取引の通信には「テレックス」という古い技術が使われていました。
テレックスは自由書式の文章でやり取りするため、非効率で人的ミスも起こりやすいという大きな課題を抱えていたのです。
そこで、取引情報を標準化し、通信を自動化・効率化する目的で欧米の銀行が中心となってSWIFTが設立されました。この歴史的背景から、SWIFTがいかに国際金融取引の近代化に貢献したかがわかります。
海外送金でSWIFTとは何ですか?

海外送金におけるSWIFTとは、国境を越えて銀行から銀行へお金を送る際に、その手続きの指示を出すための「事実上の国際標準システム」です。
日本から海外の銀行へ、あるいは海外から日本の銀行へ送金する場合、ほとんどのケースでこのSWIFTネットワークが利用されます。
国内の銀行間送金であれば、各国の中央銀行が運営するシステム(日本の場合は「日銀ネット」)を通じて行われます。
しかし、世界共通の中央銀行は存在しないため、国際送金では銀行同士が個別に「コルレス契約」という提携を結び、お互いの口座を通じて資金を決済する必要があるのです。
SWIFTは、このコルレス契約を結んだ銀行間で「これからA銀行からB銀行へ、XXドルを送金します」といった送金指示のメッセージを、安全かつ確実に伝達する役割を担います。
この仕組みがあるからこそ、私たちは世界中の人々と安全にお金のやり取りができるのです。
送金メッセージの仕組み

SWIFTの仕組みを理解する上で最も重要なのは、SWIFTが実際に「お金」そのものを送っているわけではないという点です。
SWIFTの役割は、あくまで「支払い指示」という電子的なメッセージ(電文)を送受信することにあります。
この仕組みは、郵便局に例えると分かりやすいかもしれません。
手紙(支払い指示メッセージ)を書いてポストに投函すると、郵便局のネットワークを通じて相手の住所(受取人銀行)に届けられます。
手紙の中身を見て、相手が行動を起こします。
SWIFTもこれと同様で、送金元の銀行がSWIFTネットワークを通じて支払い指示メッセージを送ると、それを受け取った受取先の銀行が、自らの口座の残高を動かして実際の入金処理を行うのです。
つまり、お金の実際の動きは各銀行が保有する「コルレス銀行口座」の中で行われ、SWIFTはその動きを指示するための通信インフラとして機能します。
このメッセージングと実際の資金移動が連携することで、国際送金が成り立っています。
swift電文とはどんな情報のこと?

SWIFT電文とは、金融機関同士がやり取りする、標準化されたフォーマットの電子的なメッセージ(データ)のことです。
この電文には、国際送金を正確に実行するために必要な情報が網羅的に含まれています。
自由な文章ではなく、全ての情報が決められた形式で記述されているため、世界中のどの銀行のコンピュータでも自動的に処理できるようになっています。これによって、迅速かつ正確な取引が実現するのです。
主な電文の内容
電文に含まれる主な情報には、以下のようなものがあります。
- 送金人情報: 送金する人の氏名、住所、口座番号
- 受取人情報: お金を受け取る人の氏名、住所、口座番号
- 送金元の銀行情報: 銀行名、支店名、SWIFTコード
- 受取先の銀行情報: 銀行名、支店名、SWIFTコード
- 中継銀行(コルレス銀行)情報: 必要に応じて経由する銀行のSWIFTコード
- 送金内容: 通貨の種類(例: USD, EUR)、金額
- 送金目的: 取引の内容(例: 商品代金の支払い)
- 手数料負担者情報: 送金手数料をどちらが負担するかの指示
これらの情報が暗号化された上で、SWIFULネットワークを通じて安全に伝達されます。
swiftの仕組みをわかりやすく解説
メモ
- 国際送金で使われるswiftコード
- スイフトコードとビックコードの違いは何ですか?
- swiftコードの例:三井住友銀行
- 気になる送金の手数料
国際送金で使われるswiftコード

SWIFTコードとは、SWIFTネットワーク上で金融機関を特定するために、各銀行に割り当てられた世界共通の識別コードです。
国際標準化機構(ISO)によって「ISO 9362」として規格化されており、8桁または11桁のアルファベットと数字で構成されています。
海外送金を行う際には、受取人の口座番号や氏名、住所に加えて、このSWIFTコードを正確に指定する必要があります。
もしこのコードを間違えてしまうと、送金メッセージが目的の銀行に届かず、送金が遅延したり、組み戻し(返金)になったりする原因となるため、注意が求められます。
SWIFTコードの構造
SWIFTコードは、以下の4つの要素で構成されており、それぞれが特定の意味を持っています。
11桁の場合は、最後の3桁が支店コードを示します。本店宛の送金や、特に支店の指定がない場合は8桁のコードが使用されるか、末尾に「XXX」が付加されます。
スイフトコードとビックコードの違いは何ですか?
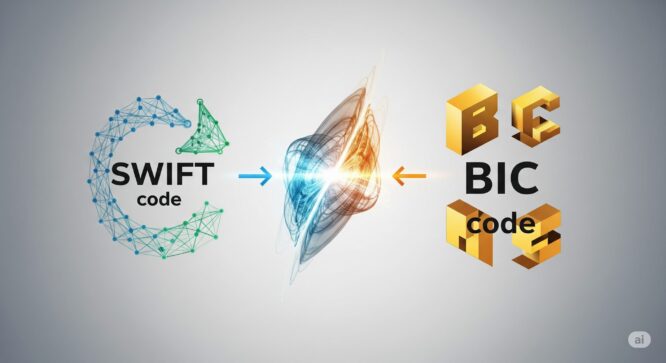
結論から言うと、スイフトコード(SWIFT code)とビックコード(BIC code)は、呼び方が違うだけで、指しているものは全く同じです。両者に機能的な違いはありません。
- BIC(ビック)コード: "Bank Identifier Code" の略で、ISO(国際標準化機構)が定めた金融機関識別コードの公式な名称です。金融業界の正式な文書などでは、こちらの呼称が使われることが多くあります。
- SWIFT(スイフト)コード: BICが、SWIFTのネットワークシステムで主に使われていることから、一般的に広く浸透した通称です。海外送金の手続きを案内するウェブサイトや申込書では、こちらの名称が使われることが非常に多く見られます。
したがって、「受取先のBICコードを教えてください」と聞かれた場合も、「SWIFTコードを教えてください」と聞かれた場合も、同じ8桁または11桁のコードを伝えれば問題ありません。
海外の送金相手によってはBICコードという言葉を使う人もいるため、「SWIFTコードとBICコードは同じもの」と覚えておくと、やり取りがスムーズに進みます。
swiftコードの例:三井住友銀行

具体的なSWIFTコードの例として、日本の主要銀行である三井住友銀行(SMBC)を見てみましょう。
三井住友銀行のSWIFTコードは 「SMBCJPJT」 です。
この8桁のコードを分解すると、以下のようになります。
- SMBC: 金融機関コード(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)
- JP: 国名コード(Japan)
- JT: 所在地コード(Tokyo)
このコードは、三井住友銀行の「本店」を指します。
海外から三井住友銀行のいずれかの支店の口座へ送金する場合、基本的にはこの本店コード「SMBCJPJT」を指定すれば、銀行側で適切な口座へ振り分けてくれます。
一部の海外金融機関では11桁のコードを要求されることがありますが、その場合は末尾に「XXX」を追加して「SMBCJPJTXXX」とすれば問題ありません。
個別の支店コードは通常不要ですが、もし必要になった場合は、取引支店に直接問い合わせるのが最も確実です。
気になるswift送金の手数料

SWIFTを利用した海外送金は、その仕組みの複雑さから、複数の手数料が発生し、合計コストが高額になりがちです。どのような手数料がかかるのかを事前に把握しておくことが、想定外の出費を避けるために大切になります。
主な手数料は、送金する側と受け取る側の両方で発生する可能性があります。
海外送金にかかる主な手数料の内訳
特に注意が必要なのは「コルレス手数料」です。
送金元の銀行と受取先の銀行が直接提携していない場合、複数の銀行を経由してリレー形式で送金されます。
その経由する銀行ごと手数料を徴収するため、最終的に受取人が手にする金額が、送金額から差し引かれて目減りしてしまうケースが多くあります。
また、「為替手数料」は手数料として明記されず、銀行が公表する為替レート(TTSレート)に組み込まれているため「隠れコスト」となりがちです。
送金手数料の安さだけでなく、適用される為替レートも確認することが、総コストを把握する上で重要になります。
まとめ:swiftとは何かをわかりやすく
- SWIFTは「国際銀行間金融通信協会」の略称
- 世界中の金融機関が加盟するベルギー本部の協同組合が運営
- 金融機関同士で支払い指示などのメッセージをやり取りするネットワーク
- SWIFT自体が資金を移動させる銀行ではない
- 役割は安全な情報伝達を行うメッセンジャー
- 海外送金における事実上の国際標準インフラ
- 1973年にテレックスに代わる効率的なシステムとして設立
- 送金にはSWIFTコード(BICコード)という世界共通の識別コードが必要
- SWIFTコードは8桁または11桁の英数字で構成される
- 構成要素は金融機関・国・所在地・支店コード
- SWIFTコードとBICコードは同じものを指す
- 送金手数料は複数の種類があり高額になりがち
- 主な手数料には送金手数料、コルレス手数料、受取手数料、為替手数料がある
- コルレス手数料は中継銀行に支払う費用で送金額から引かれることがある
- 為替手数料は銀行の為替レートに内包される「隠れコスト」になりやすい
