金融業界で「ISO20022」という言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。しかし、iso20022 とは何か、その読み方や、私たちの取引にいつからどのような影響があるのか、正確に理解している方はまだ少ないかもしれません。
この新しい国際規格への移行は、三菱ufjのようなメガバンクから地域の信用金庫、さらには国内の送金をつかさどる全銀システムに至るまで、金融界全体で進められています。
また、最近では仮想通貨との関連性も大きな注目を集めており、ISO20022に準拠した通貨は何か、そしてISO20022と仮想通貨の本格的な連携はいつから始まるのか、といった疑問も生まれています。
この記事では、iso20022とは簡単に言うと何なのか、という基本的な内容から、金融機関や仮想通貨への具体的な影響まで、網羅的に解説していきます。
ポイント
- ISO20022の基本的な意味や移行スケジュールがわかる
- 銀行や全銀システムなど国内金融機関の対応状況を把握できる
- XRPなどISO20022関連の仮想通貨について理解が深まる
- 今後の金融取引で企業や個人に求められる対応が明確になる
この記事の目次
iso20022 とは?基本をわかりやすく解説
メモ
- iso20022とは簡単に言うと何?
- iso20022の正しい読み方
- 新フォーマットはいつから開始?
- iso20022への移行における課題
- 全銀システムとの関連性について
iso20022とは簡単に言うと何?

ISO20022とは、一言で表すならば、金融機関同士が送金などの情報をやり取りする際の「世界共通のルール(通信メッセージの国際標準規格)」のことです。これまで金融機関が使用してきた情報の形式は、国や金融システムごとに異なり、長い間大きな変更がありませんでした。
なぜなら、これまでの形式は作られた時代が古く、現代のデジタル社会のニーズに対応しきれないという問題があったからです。例えば、送金情報に含められる文字数に制限があったり、情報の内訳が不明確だったりしました。
ISO20022では、XMLという柔軟性の高い言語が採用されています。これにより、送金データにこれまで以上の豊富な情報を持たせることが可能となります。
例えば、住所を「国」「都道府県」「市区町村」「番地」のように細かく分けて記述できるため、機械が自動で情報を正確に読み取れるようになります。
このように、情報の構造化と情報量の増加が実現することで、送金処理のスピードアップや、マネーロンダリング対策の精度向上といった、多くのメリットが期待されているのです。
従来のフォーマットとISO20022の比較
正しい読み方
ISO20022の最も一般的な読み方は、「アイエスオーにまんにじゅうに」です。
「ISO」は "International Organization for Standardization" すなわち「国際標準化機構」の略称です。続く数字の「20022」は、金融業界の関係者の間では「にまんにじゅうに」と読まれています。
もちろん、人によっては数字を一つずつ「にーぜろーぜろーにーにー」と読む場合もありますが、どちらの読み方でも意味は通じます。
ただ、金融関連のニュースや公式な資料に触れる際には、「にまんにじゅうに」という読み方が主流であると覚えておくとスムーズでしょう。
新フォーマットはいつから開始?
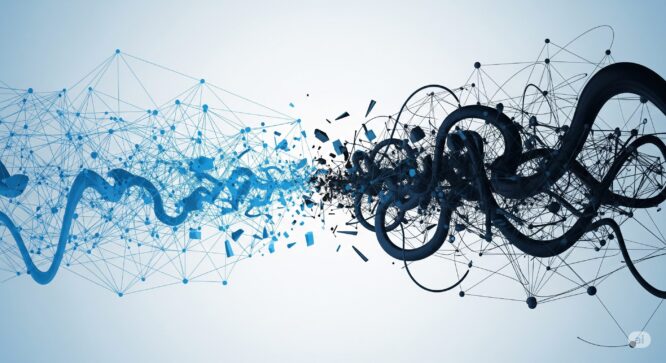
ISO20022への移行は、すでに始まっています。特に、国際的な銀行間の送金ネットワークを提供しているSWIFT(国際銀行間通信協会)では、2023年3月から新しいフォーマットの利用を開始しました。
そして、現在設定されている完全移行の期限は「2025年11月」です。この日までに、世界中の多くの金融機関は、従来のフォーマットからISO20022に準拠した新フォーマットへ完全に切り替えることが求められています。
つまり、2023年3月から2025年11月までは、新旧両方のフォーマットが併存する移行期間と位置づけられています。この期間中に、各金融機関や関連企業はシステムの改修や業務プロセスの見直しを進めていくことになります。
ただし、これはあくまでSWIFTが定める国際的なスケジュールです。個別の国や金融機関の対応スケジュールは異なる場合があるため、ご自身が取引している銀行などの公式発表を注意深く確認することが大切になります。
iso20022への移行における課題
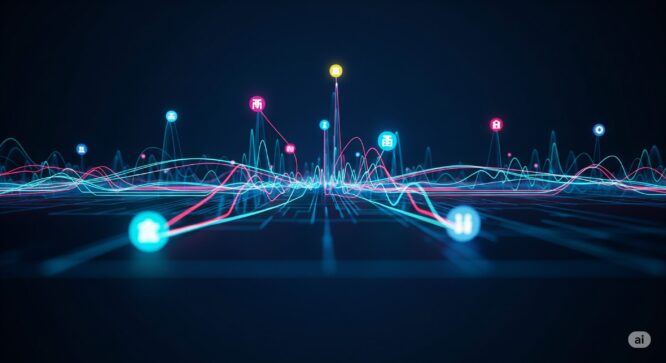
ISO20022への移行は金融取引の効率化や高度化に大きく貢献する一方で、いくつかの課題や注意点も存在します。事業者や金融機関が直面する主なデメリットやハードルは、主に次の2点です。
第一に、システム改修に伴うコストと手間が挙げられます。企業が外国送金や国内振込で利用している会計システムや販売管理システムなどを、ISO20022の新しいフォーマットに対応させる必要があります。この改修には専門的な知識が必要であり、相応の開発費用や時間が発生することは避けられません。
第二の課題は、新旧フォーマットの併存期間中に発生しうる「データ欠落リスク」です。ISO20022は多くの情報を含めることができますが、従来のフォーマットは情報量が限られています。
このため、ISO20022形式の豊富な情報を含んだ送金データを、従来形式しか対応していないシステムで受信しようとすると、一部の情報が切り捨てられてしまう可能性があります。これは、特にマネーロンダリング対策の観点から看過できないリスクとなり得ます。
これらの課題を乗り越えるためには、計画的なシステム投資や、取引先との連携、そして移行期間中の丁寧なデータ管理が鍵となると考えられます。
全銀システムとの関連性について

日本国内の企業間取引で中心的な役割を担っている「全銀システム(全国銀行データ通信システム)」も、ISO20022と無関係ではありません。
実は、2018年12月から稼働している「全銀EDIシステム(ZEDI)」は、ISO20022に準拠したXML形式の電文フォーマットを採用しています。
EDIとは「電子的データ交換」のことで、ZEDIを利用すると、振込データに請求書番号などの詳細な商取引情報を含めることが可能です。これにより、企業の経理担当者が行っていた入金消込作業の大幅な効率化が期待できます。
しかし、そのメリットにもかかわらず、ZEDIの普及はまだ道半ばというのが現状です。主な理由として、ZEDIを利用する企業側にも会計システムなどの改修が求められるため、特に中小企業にとっては導入のハードルが高いことが挙げられます。
このため、現在も多くの企業間振込は、情報量の少ない従来の固定長フォーマット(全銀フォーマット)で行われています。
今後、国や金融機関がZEDIの利用をどのように推進していくかが、国内のDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める上で一つの焦点となるでしょう。
iso20022 とは?金融機関や仮想通貨への影響
メモ
- 三菱ufjなど銀行の対応状況
- 信用金庫の対応について
- 仮想通貨との関連性
- ISO20022に準拠した通貨は?
- 対応の仮想通貨はいつから?
三菱ufjなど銀行の対応状況

三菱UFJ銀行をはじめとする日本のメガバンクは、国際的な潮流に合わせてISO20022への対応を計画的に進めています。これらの銀行は、特に法人顧客の外国送金業務に大きな影響があるとして、積極的に情報提供や準備の呼びかけを行っています。
例えば、三菱UFJ銀行では、法人向けインターネットバンキング「BizSTATION」などを通じて、外国送金依頼のフォーマットをISO20022に準拠したものへ順次変更しています。
具体的には、送金先の住所情報を国名、都市名、番地などに細分化して入力する「構造化」への対応を顧客に求めています。
このような動きは、みずほ銀行や三井住友銀行といった他のメガバンクでも同様です。各行ともに2025年11月のSWIFTによる完全移行を見据え、システムの改修や顧客への周知を徹底しています。
企業にとっては、自社で利用している会計ソフトやERPシステムが、これらの銀行が提供する新しいフォーマットに対応できるかを確認し、必要であれば改修計画を立てることが急務となっています。
信用金庫の対応について
ISO20022への対応は、メガバンクだけの話ではありません。地域経済を支える全国の信用金庫においても、2025年11月の完全移行に向けて着実に対応準備が進められています。
多くの信用金庫は、外国送金業務を大手銀行に委託していますが、送金の依頼を受け付ける窓口として、顧客にフォーマットの変更を案内する必要があります。
例えば、一部の信用金庫では、公式サイトや店頭で顧客向けのお知らせを公表しています。その中では、外国送金を依頼する際に、受取人の住所情報を「国名」「都道府県名」「都市名」「番地」といった形で、項目ごとに分けて記入するよう協力を求めています。これは前述の通り、住所情報の「構造化」と呼ばれる対応です。
ただし、注意点として、各信用金庫によって具体的な対応開始時期や、顧客に求める手続きの詳細が異なる場合があります。
したがって、外国送金を利用する機会のある個人や企業は、日頃取引のある信用金庫の公式サイトを確認するか、窓口に直接問い合わせて、最新の情報を得ておくことが大切です。
仮想通貨との関連性

ISO20022は直接的に仮想通貨の技術を定める規格ではありません。しかし、両者の間には深い関連性があり、次世代の金融システムを構築する上で互いに影響し合う存在として注目されています。
その理由は、ISO20022が目指す「より速く、安く、透明性の高い金融取引」という目標と、一部の仮想通貨プロジェクトが掲げるビジョンが一致しているからです。現在の国際送金は、複数の銀行(コルレス銀行)を経由するため、時間がかかり手数料も高くなる傾向にあります。
ここで、ISO20022に対応した仮想通貨を「ブリッジ通貨(橋渡し役の通貨)」として活用するアイデアが生まれます。
例えば、日本円を一度仮想通貨に換え、それを瞬時に海外の受取人に送り、現地でドルなどの法定通貨に換金する仕組みです。この方法が実現すれば、従来の銀行ネットワークを介さずに、低コストでスピーディーな国際送金が可能になると期待されています。
このように、ISO20022という標準化された「情報の通り道」と、仮想通貨という新しい「価値の移転手段」が結びつくことで、これまでの金融の常識を覆すようなサービスが生まれる可能性があるのです。
ISO20022に準拠した通貨は?

ISO20022という国際規格との親和性が高い、あるいは準拠しているとされる仮想通貨(暗号資産)は複数存在します。これらの銘柄は、将来的に既存の金融システムに統合され、実用的な役割を担うのではないかという期待から投資家の注目を集めています。
代表的なものとして、以下のプロジェクトが挙げられます。
これらの通貨は、いずれもISO20022が要求するデータ構造を処理できる能力や、金融機関が求める高いセキュリティ基準を満たすことを目指して開発が進められています。
ただし、「準拠」という言葉の定義は一様ではなく、各プロジェクトの自己申告である場合も多いため、投資を検討する際には、その情報の正確性や進捗状況を慎重に見極める必要があります。
対応の仮想通貨はいつから?

「ISO20022対応の仮想通貨はいつから本格的に使われるのか」という疑問を持つ方も多いかもしれませんが、これには「特定の日付に一斉に開始する」という明確な答えはありません。
なぜならば、仮想通貨自体がISO20022という規格に「移行」するわけではないからです。正しくは、ISO20022という新しい金融メッセージのルールが普及していく過程で、そのルールと連携できる仮想通貨の実用化が段階的に進んでいく、と考えるのが適切です。
一つの大きな節目として注目されているのが、SWIFTが従来のフォーマットを廃止する2025年11月です。この時期を境に、ISO20022が金融通信のデファクトスタンダード(事実上の標準)となるため、対応する仮想通貨プロジェクトの重要性も増すと考えられます。
しかし、実際の普及ペースは、各仮想通貨の技術開発の進捗、金融機関との提携、そして世界各国の法規制の整備状況など、多くの要因に左右されます。
したがって、特定のイベントを待つのではなく、金融システム全体のデジタル化という大きな流れの中で、これらの仮想通貨がどのように組み込まれていくのか、長期的な視点で見守っていくことが求められるでしょう。
まとめ:iso20022 とは金融の未来を変える規格
- ISO20022とは金融通信メッセージの新しい国際標準規格
- 一般的には「アイエスオーにまんにじゅうに」と読む
- XML形式を採用し、従来より豊富で構造化された情報を扱える
- 送金処理の迅速化やコスト削減が期待されるメリットがある
- マネーロンダリング対策の精度向上にも貢献する
- SWIFTでは2025年11月に現行フォーマットを廃止し完全移行予定
- 移行にはシステム改修のコストや手間といった課題も伴う
- 新旧フォーマット変換時に情報が欠落するリスクに注意が必要
- 日本の全銀システムもZEDIを通じてISO20022に対応済み
- 三菱UFJ銀行などのメガバンクは顧客に対応を呼びかけている
- 信用金庫も2025年の完全移行に向けて準備を進めている
- ISO20022は仮想通貨の規格ではないが強い関連性を持つ
- XRPやXLMなどがISO20022との親和性が高い通貨として知られる
- 仮想通貨との連携は国際送金のあり方を大きく変える可能性がある
- 企業や個人は取引金融機関の対応方針を確認することが重要
